旅を語る、旅を想う
その他の読み物
おじさんパッカー 北欧編(14)
16.06.21

ノールカップ到着(NordKapp 北緯71°10’21”)
「ノールカップ」に立つ
午後8時35分。5分遅れでバスが来た。運転手にバス料金とノールカップ入場料をカードで支払う(約4千円)。先客は6人。バスは海岸線を北上。
ほどなく険しい山道に入った。岩山が眼前に迫り草木はまったくない。地肌むき出しの荒涼とした灰色の世界がどこまでも広がっている。
急斜面を抜けると穏やかな平地に出た。極北の民サーメ人のテントがあった。三角錐に丸太を組んでその上に、トナイカイの毛皮がかぶされている簡単なものだ。中で火を焚いても煙が抜けるようにテントの先が外とつながっている。

極北の民サーメ人の家(車中から)

トナカイの群れ(ネットから)
サーメ人の住まいの周りには、放牧されたトナカイがコケを食んでいた。岩にはりついた雑草とわずかな藻類がトナカイの食料源だ。
そのトナカイの乳や肉、毛皮で現地の人たちの生活が成り立っているという。
時計は午後九時を回っている。まったく人の気配が感じられない山頂付近をバスが走る。運転手の後ろから地平線の先に向けそっとカメラを構える。神様が降り立つ道筋のように、一条の光線がスポットライトのごとく山の頂を照らしている。映画のワンシーンをみるような神秘的な光景だ。
道はその頂を目指して一直線に伸び、まるで天空への道をイメージさせる。雲が重く垂れ込め、周りが暗くなってきたが、光線の当たる頂の一点だけが光っていて、そこに神が住んでいるかのような錯覚におちいる。
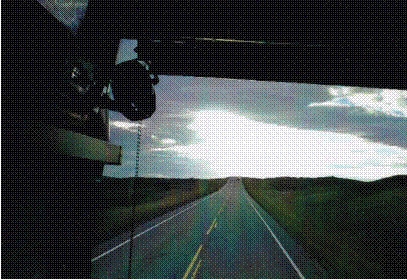
ノールカップへの道
現地時間6月26日、午後9時11分、夢にまで見たノールカップ(北岬)に到着。バスのステップを下り最果ての地に一歩を刻む。冬物のジャンパーを身につけていたがそれでも冷気で思わず身震い。
ノールカップホールの玄関に立つ。オレンジ色の門柱に、「NordKapp 71。10’21”」とある。欧州大陸最北の地だ。この先は北極点だ。
大きなガラス窓で囲われたホールに足を踏み入れる。あちこちから大型バスで到着した100人以上もの観光客で、ホール内はごった返していた。
そのままホールを抜けて海へ向かう。瓦礫を踏みしめ300メートルほど行くと、岬の先にノールカップを象徴するモニュメントが目に入った。直径2メートルほどの地球儀を模した格子状のモニュメントが、石積みの台座に乗っかっている。

念願の欧州最北端に立つ(ノールカップ
地球儀は高さ3メートル余、太さ30センチほどの鉄柱と6本の鉄の棒で支えいる。旅行ガイドで何回となく見ていただけに、「これが実物だ」と思わず両方の手を伸ばし、錆と手垢と落書きで薄汚れた鉄柱を抱きかかえた。荒いサンドペーパーのようにざらざらした感触だった。北極圏の想像もつかない厳しい風雪に立ち向かっている気概が、その荒々しい肌と冷たさから感じ取れる。
地球儀の周りは、記念撮影する観光客で人垣ができていた。何日もかけてようやくたどり着いた北の果てといっても、見るべきものは何もない。大小の石が散乱する荒涼とした岬の先に張り巡らされた落下防止の金網。その下は300メートルもの断崖が、ほぼ垂直に北極海に落ち込んでいる。
金網にもたれかかり、午前零時の太陽を眺め続けた。厚い雲が垂れ込めていて、期待した白夜の太陽を見ることができない。しかし、雲の切れ目から後光のように光が漏れ、鉛色の海面を照らす。天上からの一筋の光。スポットライトを浴びたように浮き上がる海面。風の音さえ消え静寂で神秘的だ。天地創造、神の光臨を想像させる。

午前零時の太陽を見つめる人たち(ノールカップ)
かつてここは、むやみに人が立ち入れない神聖な場所だったという。原住民サーメの人たちが神に生け贄をささげ、部族の安全を祈願した。
見渡す限り露出した岩々、暗い海に鋭く落ち込んだ断崖絶壁。容易に人を寄せつけない寒々としたこの場所で、首筋から血を流す生け贄のトナカイが柱に括りつけられている。その周りをたいまつを掲げてサーメの人たちが雄叫びをあげて踊る姿が浮かんでくる。
ノールカップ(北の岬)の名は、16世紀にイギリス人リチャード・チャンセラーが、中国への航路を探している途中で発見したという。
その後1873年にスウェーデンのオスカル2世王が訪れて以来、人々が訪れ観光地として有名になったようだ。
太陽は目線の上、15度位のところにある。光の帯が川のようにまっすぐ岸に向かって迫ってくる。金網ぞいに十数人もの人が、防寒コート、ウィンドブレーカーと冬装備で午前零時過ぎの海をただ見つめている。
突然大声がした。振り返ると、モニュメントの周りで中国からの団体客が騒いでいる。
神秘的で静寂な時間が破られた。そんな周りの空気もなんのその、中国人たちはモニュメントを背景に一人一人おどけながら写真を撮っている。
それを見ては大声ではやし立てる仲間たち。まるでお祭り騒ぎだ。傍若無人そのものだ。金網沿いの西洋人が私の顔をじろりと見た。
「おまえの仲間だろう。非常識だ」、そんな目をしていた。「私は日本人。彼らは中国人。違うの」。口にこそしなかったがそんな思いでいた。
中国人たちの大声と大はしゃぎは、この先の旅でも何回も何回もあった。
1時間ほど北極海を眺めていただろうか。手が寒さでこわばり出した。中国人の団体客が去って、モニュメントの周りに再び静寂が戻ってきた。
地球儀のモニュメントを背景に近くの観光客にシャッターを押してもらう。ノールカップへの強い思いをかなえた瞬間だ。
これまで「極北に立つぞ」といろんな人に宣言してきた。ようやく証拠写真を手に入れることができたのだ。
地球儀を離れ、300メートルほど先のノールカップホールに向かう。白い円形ドームが目印だ。午前1時を回っていても雲の切れ目から青空がのぞいている。
午前2時、「ホールを閉鎖します」と、ドア付近に立つ係員がノブに手をかけているじゃない。「ホールから出てください」と何人もの係員が、ホールにいる人々を促す。
とんでもないことになった。ノールカップホールを締め出されたのだ。夏場のこの時期は24時間開かれていると、オスロの日本大使館で確認したのに。
営業時間は午前9時から午前2時までという。次の宿泊地フィンランドのロヴァニエミへのバスは、最終が午前1時発。すでにバスは出てしまっている。
ホールは施錠された。バスはない。北極圏で路頭に迷うことになった。しかし、外は明るい、日差しも感じられる。
開館の明日九時まで外で待ったっていいじゃないか。白夜を堪能しょうと高をくくってホールを出る。モニュメントに向かう。潮が引いたように人影はない。
地下道への入り口付近に身を寄せるが冷気が付近を包み込み、体が冷えてゆくのがわかる。体を動かせば温かるのではと、歩き出す。岬一面に板状の岩石が、
まるで人の手で敷きつめられたように広がっている。槍ヶ岳とか奥穂高、前穂の頂上に散らばっていた石と形状が同じだ。
そんなことを思いながら、寒さしのぎにあてもなく歩く。
辺りが暗くなってきた。岬が深い霧に覆われ始めた。気温がぐっと低くなってきた。歩いていても、建物の蔭に身を寄せても体温がどんどん奪われてゆく。
一瞬、命の危険を感じた。
まだ灯(あかり)の残っているホールの玄関に立ち、ガラスを叩いた。戸締りしていた30半の男性が気づいてくれた。
「日本から来ました。最終バスに乗り遅れた」。それだけ話すと、
「ホールに泊めることは私の判断ではできない。ボスに聞かないと。……だけどボスはいない」。
申し訳なさそうに話す。しばらくして、彼はホールを出てきて無言で私を誘導した。視界は2メールもない。
ますます霧が深くなってゆくなか、5分ほど彼の背中を追って必死に歩いた。

命の恩人(ノールカップで働くオランダ人)
彼は、観光バスの料金徴収所のブースに私を招きいれた。楕円形をした全面ガラス張り。左右にモニター画面やパソコンが置かれていた。
三人も入れば一杯といった広さだ。
「ここなら私の判断で入れることができる」と、彼は無表情で話す。すでに午前3時を回っていた。外は乳白色で視界はゼロ。ホワイトアウト状態だ。
もしそのまま外にいたら…、とぞっとする。
彼は温かいコーヒーを入れてくれた。時折、鋭い視線を投げかけてきた。警戒しているのかも。「オランダから夏場ここに働きに来ている」という。
サッカーの話になった。日本の小野がオランダで活躍していると水を向ける。
「日本のサッカーはまだまだだが、彼はすばらしい」と30分くらい、彼は話し続けた。彼は勤務を終え就寝の時間を割いて私を助けてくれた。
太陽が沈まないのだから朝まで外にいても大丈夫だろうと軽くみた自分の甘さを悔いた。
「ホールは24時間大丈夫」と言った身の丈2メートルもあった、オスロの日本大使館員の顔が浮かぶ。
サッカーの話が一段落し、気まずい沈黙が私たちを包んだ。「日本のこと知っている?」と、日本の旅館を紹介する国民宿舎の冊子を彼に見せた。
まだ日本に行ったことがないといいながら、興味深く見ていた。日本庭園、温泉、会席料理などに興味をもったようだ。とくに、魚料理、なかでも刺身。
生で食べることなんて考えられないと、大きな手を左右に広げた。
朝5時前、仕事があるからと彼はブースを出た。30分ほどして彼が、私を呼びに来た。「ホールの宿泊客が朝食をとる時間だから、
その間入ってもいい」と。リュックを持って食堂横のソファーで足を伸ばす。30人ほどの団体客がテーブルについていた。
8時、食堂が閉じられホールの外に出た。霧が晴れ明るい日差しがホールを包んでいる。
親切な男性はどこかに消えていた。仕事に就いたようだ。9時の開館まで1時間、ホールの玄関先で待つ。
ブラジルからという4人の家族連れがやってきた。長男らしき20歳くらいの青年が閉じられたガラス戸から中をのぞきみ
「早く開けてくれんかなあ」と口走りながら、寒い寒いと、しきりに足踏みする。ブラジル人の家族と一緒に、私も小刻みに体を動かす。